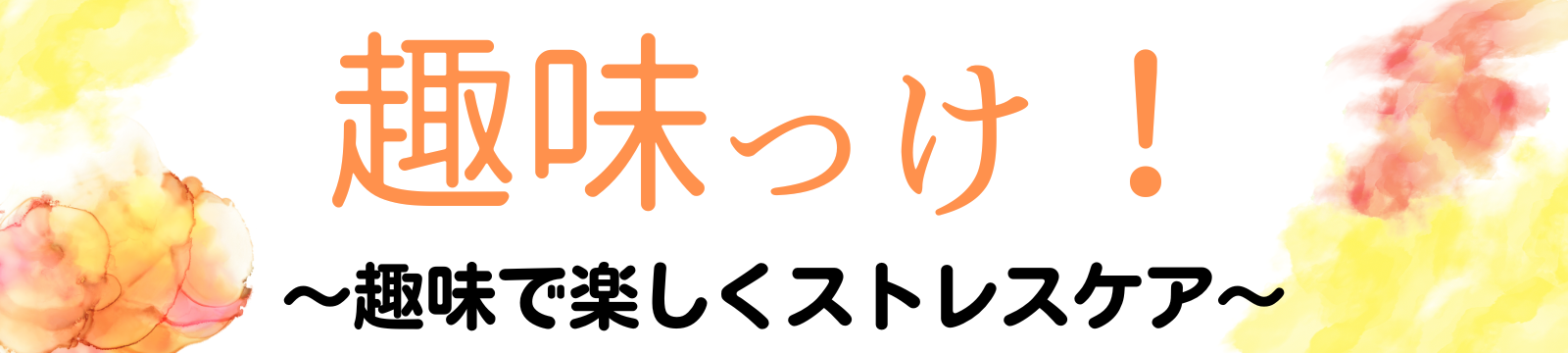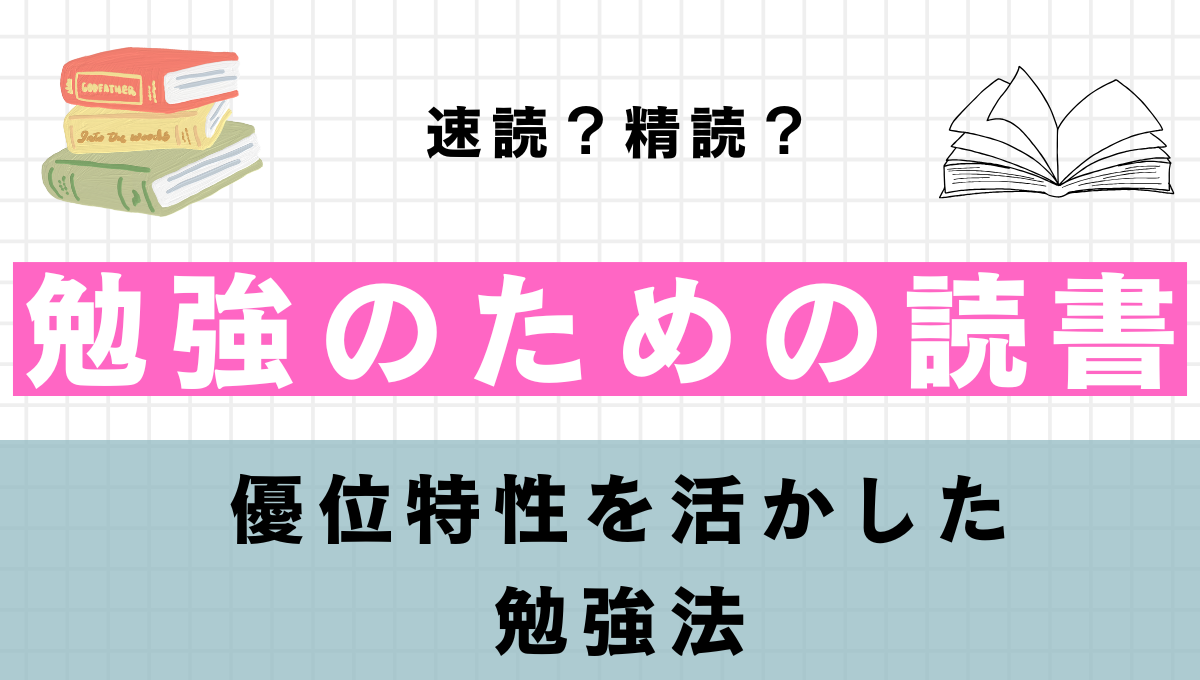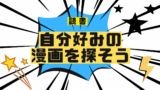こんにちは!
今回の記事では1ヶ月最低3冊以上、多い時は10冊ジャンル問わず本を読む管理人が、読書をする中で感じた疑問や効率の良い読み方についてお伝えします。皆さまが今後読書をする際のご参考になれば幸いです。
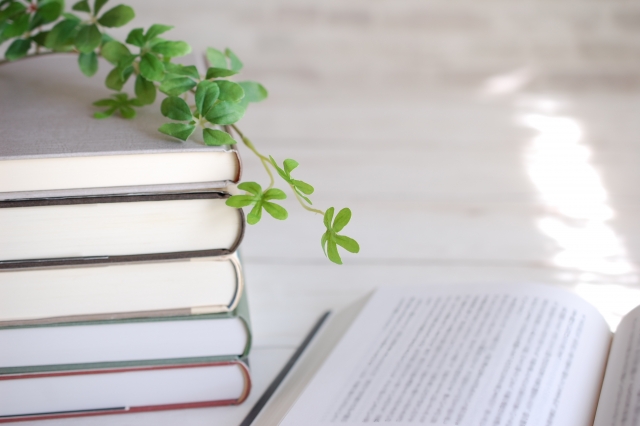
読み方の種類
読書のしかたには様々な種類があります。
例としては文章を細かく読むのではなく、要点や重要な部分を拾いながら素早く情報を得る読書法である「斜め読み」があります。
方法としては、目次や見出しを確認しながら流し読みすることで、全体の流れを把握します。こうすることで短時間で多くの情報をインプットできるというメリットがあります。
しかし一般的には速読・精読が有名ではないでしょうか?
速読
速読とは文字通り文章を速く読む技術です。実は視覚的にページを『視て』情報をインプットする読書法です。速読者はページをものすごいスピードでめくりますが、それは全体像を見て取捨選択し、自分の必要な情報のみを取り入れながら読んでいるのです。
私も実は速読の本を購入し、実行してみたのですが習得にはつながりませんでした。速読習得には目の良さや視野の広さだけではなく、物事を処理する速度や集中力も必要なのです。
速読を可能にする「脳の仕組み」もどうやら関係ありそうです。脳の認知特性というものです。詳しくは後述します。
精読
速く読むことが推奨される一方で、精読は根強い人気です。わざわざ速読と比較した精読の良さを書いた書籍が出版されるほどに、精読を推奨する人は多いです。
精読とは文章の内容を細かく吟味しながら、丁寧に読むことを指します。熟読とも呼ばれており、細部まで理解できるメリットがあります。

スロー・リーディングも素敵ですよね……!
速読習得が難しい人

実際私は動体視力や集中力が高い方ですが、視覚情報をうまく処理できないがために、速読を習得できませんでした。
誰でも練習すればできるようになるという説もありますが、これに関しては訓練時間によりけりです。
速読の練習方法には速く目を動かす訓練、想像力を養う訓練、瞑想を取り入れた集中力を養う訓練、などがあります。
それを全てクリアするには中々に時間がかかりますので、多読することが目的ならば習得する価値がありますが、内容をとにかく頭に入れたい、という人には不向きかもしれませんね。
私は特性上「向いていない」「練習時間が足りない」ため速読は断念しましたが、人によっては書籍を使用することですぐに速読をマスターできるかもしれません。

読書が苦手な人の特徴
読書が苦手な人には何かしらの特徴があります。原因としますと「集中力が途切れやすい」「本に興味がない」などが挙げられます。
集中力が途切れやすい
集中力の持続が困難な人の場合、長時間本を読むことが難しく、途中で飽きてしまうことが多いようです。また中には「文字を読むことに違和感を覚える人」もいて、活字よりも映像や音声で情報を得る方が快適だと感じることがあります。それも読書を苦手にする一つの理由となっています。
本に興味がない
最近はSNSや動画配信サービスの普及などから、年々読書離れが進んでいると言います。そのため本自体に興味を持ちづらいのも一つ原因になっているようです。
また本は読みたいけれど興味のある本が見つからない場合もあります。その場合読書の習慣が身につきにくく、結果として読書を避けてしまう傾向があるようです。
精読の良さと認知特性

先ほども記載しましたが、速読と対照的に本をゆっくりと味わって読むことを精読と言います。
私ははっきりと申しますと、精読も速読も読書に向いているかいないかが、頭に入ってくるかを決めていると考えています。
それこそ脳の特性『人が情報を処理する際に得意とする認知のスタイル』が、読書が得意な人と苦手な人がいることを決めています。
ある人は視覚的に処理することが得意でも、別のある人は聴覚的に処理することに秀でていたりします。それが個人個人の脳の使い方の癖であり、特性なのです。
特性の種類
ざっと特性の種類を挙げてみます。
視覚優位
- 画像や映像で情報を理解しやすい
- 地図や図表を使った学習が得意
- 物事を空間的に把握する能力が高い
言語優位
- 文章を読んで理解するのが得意
- 言葉を使った説明や論理的な思考が得意
- 書くことで記憶を定着させやすい
聴覚優位
- 音声での情報処理が得意
- 会話や講義を聞いて理解しやすい
- 音楽やリズムを活用した学習が効果的
この三つが感覚の特性です。
管理人の余談
余談ではありますが、私は耳から入ってきた情報を処理するのが得意でありながら、聴覚過敏を持っていますので、聴覚からの情報過多だと疲労感が出てしまいます。
また体を動かしながらお手本どおりに動くのが記憶に定着しやすいと自覚していますので、読書の際は独り言を呟いたり突っ込んだりして読んでいます。

え、そうなん……嘘やん

なんでやねん!
周りからしてみれば変な人なのですが……。
しかし自分が得意ではない方法で勉強をしてしまうと、それだけで脳が疲弊してしまい、勉強効率が下がってしまうこともあります。
読書も同じで、声に出しながら覚えるほうがやりやすい人は、オーディオブックの購入や、ラジオ・ポッドキャスト番組を教材にするのがいいかもしれません。
結果私はその人に合った読書方法が一番よいと考えております。
また思わぬところから情報を得ることができるかもしれません。それは漫画です。
漫画の魅力
漫画は読書の出入り口として活用できます。今まで本が苦手で読書をしてこなかった人にとっては、書籍を開くのも億劫かもしれません。その際ハードルが低い漫画を読むことから始めるのもいいかもしれません。
また難しい内容を本ではなく漫画で覚えるというのも良いですね。医療系の漫画・法律系の漫画・科学系の漫画……。世の中には難しいジャンルの漫画で表現した作品が多々あります。
「そういった分野に興味はあるけれど専門書は……。」と言った方に漫画はおすすめです。
個人に合った勉強方法

現代では紙の本だけが読書、というわけではありませんので、個人個人に合った方法で勉強をしていけばストレスも最小限に抑えられます。
読書方法も勉強方法も、目標をしっかりと決めることが大切です。
今月は10冊読むぞ! という場合は速読。資格取得のために1冊絶対頭に入れる! という場合は精読。
そして自分にどんな勉強方法が合っているかを振り返ってみて、いろんな要素を鑑みて読書方法を決めてみてはどうでしょうか?
結論
速読には様々な能力が必要→ただ読書が好きなだけで習得できる技術とは言えない
書籍を使用すると速読はマスターしやすい→速読のコツが書かれた書籍は習得に有効
速読が向いていない人もいる→集中力や視覚情報処理速度も速読には必要
得意な勉強方法は個人によって違う→自分に合った勉強方法を探すべし!
以上ライターのあさきでした。閲覧ありがとうございました!